- サステナビリティ
ホンジュラス訪問レポート2025〜生産国でのクオリティ追求と私たちの課題〜

カフェやコーヒーショップでは、目の前のバリスタがコーヒーを一杯一杯作る様子が見え、品質の追求を感じる消費者も多いでしょう。では生産国ではどのようにクオリティを追求しているのでしょうか。今回の記事では、生産国での品質管理がどのように行われているのか、ホンジュラスの輸出業者やコーヒー生産者を訪問を通して見えたことをご紹介します。
ホンジュラスのコーヒー名産地サンタバルバラ
例年通り今年5月もホンジュラス・サンタバルバラを訪れました。ホンジュラスで「コーヒーと言えばサンタバルバラ」と言っても過言ではないこの生産地域。私たちが取引をしているホンジュラスの輸出業者サンビセンテもサンタバルバラ地域のペーニャブランカという街にあり、地域のスペシャルティコーヒーの根幹を担っています。サンビセンテの中心メンバーも自身の農園を持つ生産者であり、アンヘルさんは、ONIBUS COFFEEが継続購入している生産者の一人です。アンヘルさんをはじめサンタバルバラの生産者たちは、高く評価されるテロワールに加え、品質向上の試みを行っています。
2025年新たな取り組み「ドライングを解明する」
コーヒーの品質に関わる要素には、産地・標高・品種・精製方法などがありますが、この後に続くドライング(乾燥)も、品質を左右する非常に重要な工程と言われています。
このコーヒーの精製方法・乾燥日数などには、明確な規定がありません。例えば、一口に「ウォッシュド」と呼ばれる精製方法でも、ミューシレージ(種子を覆う粘着質)を取り除くためだけにソーキングを行っている場合もあれば、水に浸けたまま発酵を行っているケースもあります。これらは全て、単純に「ウォッシュド」と呼んでも問題になりません。
同じように、コーヒーのドライングにも教科書はありません。乾燥にかける日数は、気温・日照時間(日差しの強さ)・天気・乾燥させている豆のプロセス(ウォッシュド・ナチュラルなど)などの条件により変わりますが、基本的にはコーヒー豆を目安の水分値になるまで乾燥させるということだけが共通しています。明確に何日という定義はない一方で、乾燥にかける日数が短すぎると、豆の品質の劣化が早まったり、フレーバーに影響が出るなど品質に良くない影響を与えるということが知られていてます。そのため、多くの生産者は温度や日の当たり具合を調整することにより12〜25日くらいかけて乾燥させています。それぞれの生産者の経験によるものも多いですが、雨を避けるために乾燥棚に屋根を付けた結果、日差しを遮る効果があり乾燥にかける日数が伸びたなど、環境的な要因も相まっていることも多いです。
コーヒーの品質に与える影響が複雑でもあるドライング。このプロセスをより「解明」することで、品質の向上が期待できると探るアンヘルさんは、現在2つのプロジェクトを行っています。
写真左:アフリカンベッド 写真右:低温長時間ドライングを検証しているコンテナ
①アフリカンベッド改良:
アフリカンベッド*が設置されている小屋(写真左の大きいビニールハウスのようなもの)の屋根に、日光をある程度遮断できる半透明グレーの素材を使用。ドアの開閉以外に、側面のビニールを捲り上げ、温度の通気を促して温度の調節ができるように設計しています。これは、日本の果物栽培のビニールハウスでも見られるものと同じ仕組みです。
*コーヒーを乾燥させるための高床式の乾燥棚
②冷暗所スロードライング:
14度〜18度に保たれた冷暗所の中に、除湿機を設置し、スロードライング(長期間乾燥)を検証中。こちらは完全に検証ベースで、普段と違う環境でドライングし、そのプロセスと最終カップのクオリティで結果を判断するとのこと。検証には、ONIBUSでも販売しているエルタンゴのゲイシャが使われていました。今後、ロットのカップを取れる日が来る事はあるのか楽しみなところです。
生産者たちの試み
サンタバルバラ地域には、COE*常連のような名だたる実力を持つ生産者達が多くいます。彼らは農園にある品種の植え替えや、収穫ロットを細かく分けて精製方法を試すことにより、常に改良点を探しています。実際にカッピングテーブルにこれらのコーヒーが並ぶのは、より良いものを作ろうという生産者の思いが目にみえる瞬間です。
サンビセンテは、生産者に対してのアドバイスを日常的に行っています。また肥料の使い方・お金の使い方などを含めた年6回のセミナーも生産地で実施しています。先述のサンビセンテで行われているドライングの検証も、生産者へ随時ノウハウが共有されていくものです。このようなサポート体制があることで、生産者は常に高品質なコーヒー生産を目指すことができるのです。
*カップオブエクセレンス。コーヒーの品評会
持続可能な生産と品質向上を実現するホンジュラスのコーヒーシーン
今でこそ、その名が知れ渡り世界中からロースターが訪ねて来るようなサンビセンテですが、最初からその環境が用意されていたわけではありません。
サンビセンテは、コモディティコーヒーを取り扱う輸出業者としてスタート。スペシャルティコーヒーの生産が広まっていったのは2001年以降のことです。そのため、現在農園に植えられているコーヒーノキのほとんどは、生産者がイチから植えたものです。家族が持っている農園を引き継いで指折りのスペシャルティコーヒー農園に進化させた人、親戚が売り払ってしまった土地を買い直してコーヒー生産を始めた人、コーヒーを諦めて一度アメリカに出稼ぎに行くもスペシャルティコーヒー生産に戻ってきた人ーーさまざまな背景を抱えながら、COEなどの品評会にコーヒーを出品することで、そのクオリティの高さが確実なものとして評価されてきました。得た資金は、農園までの道の補修や設備投資・生産費用に回し、クオリティを向上させ続ける環境を整えています。

私はCOEを「オークション」としか思っていなかったのですが、このサンタバルバラで産地を見て考えが変わりました。特別に農園の設備が整っている訳ではない小規模農家が品質を評価され、得た資金を投資に回し、さらに良いものを継続的に生産できる環境を整えていく。そしてこれが、この地域全体で行われていることには驚きを隠せません。良いものを生産するとどのような変化があるのか、実際に体感があるからこそ、崩れないクオリティを保ち続けることができるのかもしれません。コーヒー生産は農業であり、結果を見るまでに時間が掛かりますが、その忍耐力と誠実さには、頭が下がる思いです。
サンタバルバラ地域では、世界の名だたるロースターが、生産者に対し直接資金援助や精製方法のリクエストを行いながらコーヒー精製を行っているケースも見受けられます。彼らは、この消費国からの申し出を単純なリクエストとして受け取るのではなく、品質を良くするためのヒントとして受け取っていました。今回の訪問で会った生産者の一人は、新しい方法を提案された際「まだ手元に2袋分(60kg)のコーヒーがあるので、それで試してみるよ」と言っていました。彼らのこの姿勢こそが、一番の強みであり、高品質なコーヒーが生み出され続ける所以と言えるでしょう。
さいごに
世界的な産業であるコーヒーは、生産からカフェに至るまでさまざまな人の手が関わっています。
生産地には気候変動や人手不足が襲いかかる一方で、私たちロースターには、為替変動や品質・購入量の確保、豆の品質を存分に発揮できるような焙煎・抽出スキルの向上というテーマがあります。それぞれの立場や直面する課題の質は違ってもクオリティの追求や直面する課題、状況をより良くしようという本質的なものについては、みな同じものを見ていると思います。各分野を追求する人たちの連携で生み出されているのがスペシャルティコーヒーであり、産地に行くとコーヒーを届ける自分たちの役割を全うしようという気持ちが強くなります。
現在、サンタバルバラ地域では、20代の次世代の生産者が育ち始めていたり、サンビセンテがある地域で生まれた子達が農業大学を卒業し、コーヒー産業に戻ってきていたりと良いニュースも存在します。コーヒー産業では課題も多く語られますが、引き続き美味しいコーヒーと明るいニュースを届けられるように取り組んでいきます。
今回の訪問で買い付けたロットは、秋ごろに販売開始予定です。まだ少し先ですが、楽しみにお待ちください!
text and photo by Chiaki Kuwahara











![コーヒーギフト[オニバスブレンド&シングルオリジンセット]](http://onibuscoffee.com/cdn/shop/files/DSCF6400.png?v=1764237384&width=533)
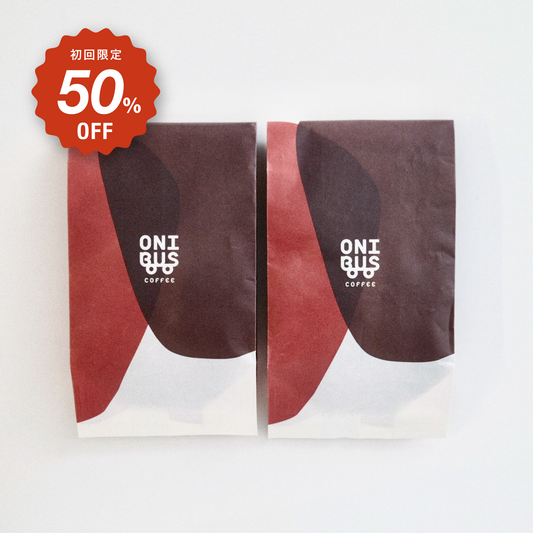
![コーヒーギフト [オニバスブレンド&カップ・ソーサーセット]](http://onibuscoffee.com/cdn/shop/files/DSCF6421-2.jpg?v=1764240210&width=533)