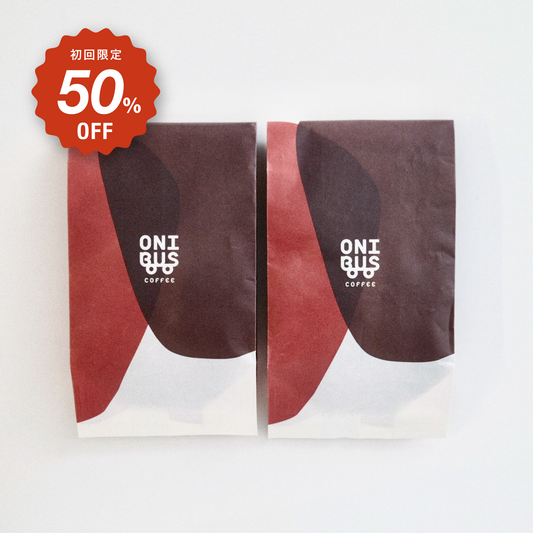- サステナビリティ
ビジネスと環境のちょうどいい関係を探して カーボンオーディット2024-2025

『117.88トン』の重み
117.88トンーONIBUSが事業活動で排出した1年分のCO2の量です。
ONIBUSでは、事業をすることでコミュニティや環境にどのような影響を与えているかを数値にして計測しています。CO2排出量の可視化と評価するカーボンオーディットもそのひとつで、ONIBUSでは2022年から実施しています。
117.88トンと聞いても、なかなか想像がつかないものです。
そこでみなさんの手に渡るコーヒー1杯あたりに換算してみます。1年で国内全7店舗で販売したコーヒーの杯数は392,319杯だったので117.88トン を 392,319杯 で割ってみます。
117.88(t) ÷ 392,319 = 300.5(g)
1杯のコーヒーを提供するのに排出するCO2の量は300.5gだということがわかります。コーヒー1杯の液体量は約200gなので、コーヒーよりもそれを作る際に排出しているCO2の方が多いことになります。

なんだか少し複雑な気持ちになる結果ですが、同様の計算で1杯あたりのCO2排出量が346gだった昨年と比べると実は13%も少ない数字になりました。
この数字を紐解いていきます。
ONIBUSでは以下の情報をもとにCO2排出量を計測しています。
◾️計測期間:1年(2024年9月~2025年8月)
◾️計測範囲:国内全店舗
Scope1 店舗、事業所でのガスの使用量より算出
Scope2 店舗、事業所での電気使用量より算出
Scope3(一部)移動距離、移動手段により算出

冒頭に書いた、今期の排出量合計117.88トンがその結果です。そのうち41.70トンが焙煎や調理を中心としたガスの消費によるもの(Scope1)、59.7トンが照明や空調やコーヒーマシンなど電気の消費によるもの(Scope2)、16.5トンがコーヒー買付やイベントの際の飛行機移動などによるもの(Scope3)だということがわかりました。
店舗ごとに見ていきます。

八雲店が40.8トンで総排出量の34%を占めています。八雲店は焙煎所を兼ねた施設で、全店舗で使う分や卸先へ送る全てのコーヒーの製造拠点です。焙煎には熱が必要です。この時に多くのガスを燃焼させるので排出量が多くなります。
2022-23年の調査では八雲のCO2排出量は56.8トンでした。その頃に比べ、焙煎量は増えているのですが、CO2の排出量は大幅に少なくなりました。メインで使う焙煎機を大きなサイズに変えてガスの効率が良くなったことが要因です。生産性の向上を目指したところ、エネルギー効率にも効果が出たのは嬉しい結果です。
さらに電力にも大きな進化が。2025年4月には、WE MAKE ENERGY のサポートで太陽光パネルを設置し自家発電と電力自給を開始しました。するとWE MAKE ENERGYの方が事前に予測していた数値を大きく上回る発電量を記録。天気の良いある日、八雲の発電量をモニタリングをしていたWE MAKE ENERGYチーム内で「何かの間違い?」とちょっとした騒動になったそうです。調査すると、採用したパネルの発電効率の良さに加え、屋根の大きさや角度、周囲の環境など、八雲は太陽光発電に極めて適していたということがわかりました。
この効果は絶大で、稼動開始後わずか数ヶ月でCO2 1.5トン分の削減に繋がりました。購入するのが当たり前だった電気を自給できて、しかも余剰分を分られるということの気持ち良さも実感しています。
次いで、排出量25.5トンで22%を占めているのが自由が丘店です。キッチンや菓子製造設備があることでこの数字になっています。八雲店同様、他店舗の分の製造を担う店舗ではCO2排出量も集約されます。比較的面積の広い店舗でもあるため、特に夏場・冬場の空調でエネルギー使用量が増加する傾向にあります。昨今の酷暑の影響はここにもあらわれます。
八雲や自由が丘のような製造設備を持たない店舗はどうでしょうか。那須店(10.8トン)、中目黒駅前店(10.7トン)、ALCB渋谷一丁目店(7.9トン)、ALCB道玄坂店(4.3トン)の順になっていて、ほぼ店舗の面積順に並んでいます。
圧倒的に少ないのが中目黒三丁目店です。2024年9月にオープンしたこの店の1年間のCO2排出量は1.4トン。7店舗の中でも一番狭いALCB道玄坂の3分の1のCO2排出量にとどまっています。理由は明確で、この店では”100%再生可能エネルギー”を使用しているからです。100%再生可能エネルギーは電力を消費しても排出するCO2がゼロのエネルギー。もし中目黒三丁目店が通常の電力を使用していたら、8トン程度の排出量になります。
Scope3についても少々解説。

本来であればこの項目には、従業員の通勤移動や、各サプライヤーからONIBUSまでの原材料や資材の流通、ONIBUSから卸先・オンラインショップのお客さまへの商品の流通、ごみの回収や処理などなども含まれます。しかし、その全てを追跡するのは現実的でなく、まずは計測可能な国内外の飛行機移動、新幹線移動をScope3で表しています(社用車のガソリン燃焼はScope1にあたりますが、店舗運営と切り分けるためONIBUSではScope3に入れています)。
今回の調査の結果、Scope3は16.5トンでした。主に飛行機移動によるものです。グーグルフライトを使い、ルートと人数でCO2量を割り出しています。この1年は、ケニア・ルワンダ・ホンジュラス・オーストラリア・台湾・タイなどに訪問しました。流通の透明性を高め、生産者とよりよい関係性を構築するためにしているコーヒー生産国訪問や、海外に拠点を置くパートナーとの交流は、ONIBUSの体験をより豊かにするために欠かせないものです。環境負荷の少ない活動と、ブランドが大切にしていることの両立には、矛盾があるようにも見えてしまいます。
しかし、この矛盾こそが、私たちがこれから向き合うべき大切なテーマであり、カーボンオーディットをする意義だと感じています。
「環境負荷を数値であらわして責任を明確にする」「エネルギーを見直してできることから対策をする」「生産国の人々と一緒に自然再生に取り組む」「生産地で感じたことをお客さまにストーリーとして伝える」あらゆる活動に意義を見出すことで、この課題とこれからも向き合い、ONIBUSらしさに変えていきたいと考えています。
これから
今回の結果を踏まえて、すでに取り組んだことがあります。それが、電力の切り替えです。ONIBUSは2019年頃から条件の合う店舗では、みんな電力の再生可能エネルギーを使用していましたが、”100%再生可能エネルギー”のプランではありませんでした。そのため、通常の電力よりはCO2量は少ないものの、ゼロとは言えませんでした(CO2係数はこちらを参照)。そこでONIBUSは、中目黒三丁目店に続いて今年10月より中目黒駅前店・八雲店・自由が丘店・ALCB道玄坂店100%再生可能エネルギーのプランに切り替えました。これによって店舗全体で年間約38トンのCO2削減が期待できます。

ONIBUSでは、CO2同様にごみの廃棄量やリサイクル率も測定し環境へのインパクトを注視しています。ONIBUSが事業を続けていくために、焙煎を止めたりコーヒーカスをなくしたりすることはできません。それでも、皆さんの手に届く1杯が、より環境にやさしいものになるように、そしてこれからも美味しいコーヒーが飲めるように、責任を持って取り組んでいきます。
CO2排出量を相殺してゼロにする”カーボンニュートラル”、出した以上に減らす”カーボンネガティブ”も将来に見据えつつ、当面の目標は、1杯のコーヒーあたりのCO2の排出量を、コーヒー1杯の量よりも少ない200g以下にすること。来年のレポートをご期待ください。
Text and illustration by Mai Yamada





![ホンジュラス / アンヘル・アルトゥーロ・パス・ラミレス[ゲイシャ]](http://onibuscoffee.com/cdn/shop/files/honduras_4abfb3f7-8f5a-4f23-8061-001ec27cb58b.png?v=1725328486&width=533)