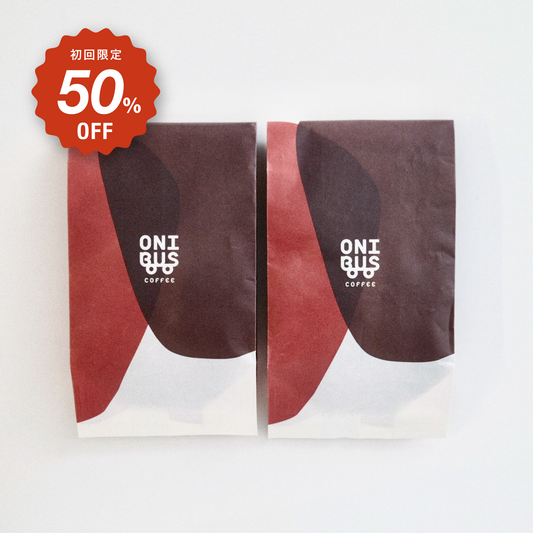- メンバー / はたらく
土に触れて、発酵を感じる!ONIBUSの社員研修

日々、コーヒーに向き合うONIBUSのスタッフ。「コーヒーで、街と暮らしを豊かにする」という共通のビジョンを持ちながらも、人数も店舗も増え、お互い顔を合わせる機会は少なくなってしまいました。
そこで、店舗から離れてみんなで社員研修へ!研修といっても勉強会や見学でなく私たちがしたのは「田植え&稲刈り」です。ONIBUSらしく土と発酵に触れる2日間になりました。
微生物が息づく寺田本家へ

5月末、約20名の社員スタッフが向かったのは千葉県香取郡にある『寺田本家』。江戸時代から350年続く酒蔵です。
先代が始めた”自然酒”は、無農薬米を使い、添加物は一切使わず、蔵付きの微生物たちの力で発酵させて造る酒で寺田本家の代名詞的存在。24代目の寺田勝さんが代表を務める現在も、できるだけ手作業で、昔ながらの道具や方法を用いて、微生物と一緒に酒造りに励んでいます。
ONIBUS COFFEE八雲店の床の一部に使われている古材は、寺田本家の古い酒蔵の解体材。そんな繋がりもあります。

蔵を訪れると目に入るのは、木桶やタンクや大小さまざまな道具たち。そのどれもが丁寧に手入れされていて、長く大切に使われてきたことがわかりました。しっとりした蔵の空気や香りには、目に見えないはずの微生物たちがのびのびと息づいている様子があります。そして20名を超える大人たちがゾロゾロお邪魔しても快く受け入れてくれた寺田本家のみなさんからは、多様に異なる個性を受け入れる寛大さが窺えました。
初夏の田植え

今回の社員研修の主なイベントは田植えです。蔵から車で10分ほど離れた水田に向かいます。谷間にある水田は、かつて放棄されていた場所を寺田本家のみなさんが開墾して復活させたものだそう。
1.6反(テニスコート4面くらい)の大きさの田んぼに、中生神力という在来種のコメの苗を植えていきます。ほとんどのメンバーにとって初めての田植えです。カエルや虫たちが暮らす田んぼに裸足で踏み入ると、まずは土の冷たさや足を取られる感触に新鮮な驚きを覚えました。田んぼのんいたるとこで「冷たい!」「おお!」という声が次々聞こえてきます。苗の束から3本くらいを摘み取って、土に植え付けていきます。そのうち土の中でもうまくバランスが取れるようになり、泥がかかることも気にならなくなっていきました。

熱中しているうちにあっという間に作業は終了。まだ赤ちゃんの苗が、季節を経て育っていくのが楽しみになりました。
実はこの日が寺田本家の今季最後の田植えの日でした。田植えが無事に終わったことを祝う『早苗饗(さなぶり)』という農耕文化にならい、作業の後はみんなで食を共にします。自然への感謝と人々の繋がりや働きへの労いを込めた大切な行事です。
一仕事を終えた後にみんなで食べる食事の美味しさ、お酒のおいしさ(作り手の解説付き!)を実感しこの日は終了しました。
秋の稲刈り

再び寺田本家を訪れたのは約5ヶ月後の10月上旬。季節はすっかり進んで、稲刈りの時期がやってきました。
この日は関東地方に台風が迫っていましたが、幸いにも雨は降らず無事に稲刈り決行。田んぼを訪れると、前回と景色が変わったのがわかります。小さく細かった苗は地面を覆い隠すほど大きく育ち、中生神力の稲穂は風に煽られながらもしなやかに力強くありました。
稲を刈り取る人と、刈り取った稲を束にして麻紐で結いていく人が協力して作業を進めていきます。稲を根本を刈り取る時のザクザクとした感覚は、なんとも言えない気持ちよさでした。みんなが同じ空の下で同じ風を受けながら同じ仕事を黙々としていきます。

束にした稲は逆さにして干します。この稲架掛け(はさかけ)を終えたときの達成感は、ずっと腰を屈めていた姿勢からの解放に、酷暑を耐えて立派に育った稲や自然への感謝も混ざっていました。これから何日もかけてゆっくり乾燥させて、脱穀と精米をして、やっと日本酒の原料になります。
この日も作業のあとは全員でごはん。今回はONIBUSのパティスリーチームより寺田本家の酒や酒粕を使ったデザートも振る舞わせていただきました。寺田本家からもいろんな日本酒の瓶が次々と開き、どれもがユニークで驚きに満ちていました。
初夏と秋、2回に渡って寺田本家を訪問しました。実はこの間の7月にも田んぼの除草のために数名のスタッフが伺っています。季節を巡って自然の営みを知ることで、普段何気なく食べたり飲んだりするものへ、ありがたみが募ります。コーヒーも同じで、遠い国で誰かが時間をかけて作っているということが想像できるはず。
寺田本家の発酵するチーム

田植えと稲刈りという貴重な体験を通じて、日常で会う機会の減ったメンバーが一緒に土に触れて作業をすることができました。本当に気持ちの良い時間でした。
他にも印象に残ったことがあります。それは、寺田本家では仕込みや素材を混ぜ合わせる時に”唄をうたう”ことです。酵母の仕込みにかける時間や混ぜ方の強弱をこの唄で調整しているのです。蔵の中で響きわたる蔵人たちの唄声に感動を覚えました。微生物たちもコーラスのようにこの唄に呼応している気がします。

ふと、400年に渡って農業を営んでいる農家の方が「自然界ではアナログなやり方こそ精度が高い」と言っていたのを思い出しました。効率や生産性が重要視される現代ですが、アナログな方法には近代のテクノロジーでは説明できない種類の合理性があるのです。
寺田本家も350年の歴史を持ちながらも先進的に見えるのは、酒造りの概念をくつがえすような大胆な発想を持ち、個性的な日本酒を作っているから。そしてチームそのものが”発酵”しているからだと感じました。発酵していれば、物事は腐敗せずに常に新しい形で存在し続けるのです。
そして良い発酵が多様性と時間を要するように、チームもさまざまな変化を受け入れながらやがて一体感が醸成されていくのだと感じる社員研修でした。この研修で、協力することの楽しさ、自然も人も矯正ではなく寄り添うように付き合うこと、心を豊かにする体験、次の世代に繋げていく想いをたくさん得ました。

寺田本家の皆さん、一緒に参加したミコト屋の皆さんありがとうございました!
Text and photos by Mai Yamada





![ホンジュラス / アンヘル・アルトゥーロ・パス・ラミレス[ゲイシャ]](http://onibuscoffee.com/cdn/shop/files/honduras_4abfb3f7-8f5a-4f23-8061-001ec27cb58b.png?v=1725328486&width=533)