- スペシャルティコーヒー
ペルー生産国訪問 産地が担う品質管理

2025年9月下旬、ONIBUS COFFEEとしては初訪問となるペルーに行ってきました。ONIBUS COFFEEでは過去にもペルー産コーヒーを取り扱ってきましたが、実際に現地を訪れるのは今回が初めてです。
ペルーは多様な気候・自然環境を有する国で、近年スペシャルティコーヒーの生産地としても非常に注目されています。今回のブログでは、ペルー北部の訪問先の紹介とともに、現地で感じたこと、特にコーヒーの品質管理における「第三者機関」の重要性についてお話ししていきます。
ペルーのコーヒー生産地域

ペルーは、南米に位置する国で、アンデス山脈やマチュピチュ遺跡など豊かな自然と古代文明の遺産で知られています。エクアドル、ブラジル、ボリビアなど南米5カ国と国境を接し、国内に3つの気候帯(乾燥地帯・高地・熱帯雨林)といった多様な気候をもっています。
ペルーのコーヒー産地は主にアンデス山脈の東側に広がり、北部のカハマルカ、中央部のフニン、南東部のクスコ、北東部のサン・マルティンなどが代表的な地域です。高地の涼しい気候と豊かな土壌が、品質の良いコーヒー豆を育てることに繋がっているように思えます。
ペルーにおけるコーヒーの歴史は、植民地時代にヨーロッパからコーヒーが持ち込まれたことに始まります。19世紀後半にフニン県のチャンチャマヨで本格的な栽培が始まりました。その後、各地にコーヒー栽培が広まっていき、現在では国内消費に加え、輸出も拡大しました。更にフェアトレードやオーガニック認証の取得が進むなど、持続可能なコーヒー生産国としての地位を確立しつつあります。例えば、ペルーCOEは、入賞ロットにオーガニック栽培のマークが表示されており、品質の他にも栽培方法を確認する事が出来ます。

ペルーCOE2024年の入賞ロットの掲載ページ。クローバーのマークがオーガニック栽培のマークです。引用元:https://allianceforcoffeeexcellence.org/peru-2024/
数ある国内生産地の中で、今回私たちが訪れたのはペルー北部にあるカハマルカ地域です。国内でも有数のコーヒー生産地として知られ、スペシャルティコーヒーの台頭以前よりコーヒー栽培が行われてきた場所です。ハエン、サン・イグナシオ・デ・アルトと呼ばれる地域にある、輸出業者や農園を訪問しました。
Origin Coffee Lab
日本から約2日間かけて到着したのは、ハエンという街です。到着したのは夜でしたが、交通量が多く、地元のレストランや屋台が賑わっている様子が印象的でした。街の規模に対して、人口が多いためか、排気ガスの威力が凄まじく、目が痛くなるほどの空気を感じました。
そんな中心部からさほど離れていない街中に、輸出業社Origin Coffee Labがあります。2017年に代表のホセ・リベラ氏が創業し、現在では250人ほどの生産者と取引を行っています。施設内には、カッピングラボ、サンプルロースター、水分値計測機、倉庫など、品質管理に必要な設備が整っています。

Origin Coffee Labは、単なる輸出業者にとどまらず、農業技師を派遣して生産者に栽培・精製技術を指導し、品質管理をサポートします。生産者が栽培したコーヒー豆は、必ずカッピングラボで品質チェックを受け、フレーバーや欠点豆の種類、水分値などのフィードバックが行われます。生産者はそのアドバイスを元に、品質向上に向けて取り組みます。現在、特にコーヒー栽培についてのサポートは、イバンくんという青年が担っており、彼が農園を直接訪問し現地での生産アドバイスを行っています。
さらに、Origin Coffee Labでは、同じ品種でもロットごとのフレーバーが近い豆を丁寧に組み合わせてボリュームを確保するなど、マーケットの需要に合わせて繊細な工夫を重ねています。これは、カップの印象をもとにした精密な管理の元行われており、こうした活動を通じて、品質を守りながらボリュームを求める顧客にも応え、マーケットアクセスの拡大にも寄与しています。
パレスチナ農園

パレスチナ農園は、ハエンの街を更に北上した、サン・ホセ・デ・アルトに位置します。この農園を保有するアラルコンファミリーは、前述のOrigin Coffee Labと共に働く生産者です。彼らは、この土地でコーヒー生産を行う3世代目で、約5年前からOrigin Coffee Labとの取引を開始しました。
一族で約100ヘクタールの土地を保有し、コーヒー農園が約17ヘクタール、約70ヘクタールは自然保護区にあたります。現在は、兄弟のホセさん、フアンさん、アニバルさん、そしてイノセンシオさんでそれぞれ3〜4ヘクタールの農園を管理しており、栽培されている品種はブルボン、カツアイ、ゲイシャなどに加え、シドラやSL9、エチオぺなど多岐に渡ります。
代々コーヒー農園を営んでいる彼らですが、Origin Coffee Labと働き始めてからというもの、さらにコーヒーの品質を向上することが出来ていると語ります。農業技師のイバンさんや、Origin Coffee Labチームからのアドバイスにより、コーヒーの精製プロセスなどを精査し、より品質をコントロールできるようになったと話します。
アラルコンファミリーが品質の向上について実感しているように、既にコーヒー栽培の技能を持つ生産者にとっても、スペシャルティコーヒー市場の中で品質を担保していくのは難しいことです。土壌の健康状態、土地のテロワール、栽培・精製技術、また気候が全て揃ってこそ、確固たる品質が生み出されます。
また、このパレスチナ農園では、土地の持つ豊かな生態系保護を目的とした養蜂も行っています。このプロジェクトには、Origin Coffee Labなど第三者機関も参加しており、農園で働く生産者以外にも生態系保護に力を入れている様子が見て取れます。
農園を含む敷地は、約1600〜2100mの高度差があり多様な植物が生息していますが、標高が高すぎると活動により多くのエネルギーを必要とする為、蜜蜂のコロニーとしては適さないとのこと。ただ多様性があるだけでは自然は機能せず、上手くバランスを取り合う環境を作ることが大切なことが伺い知れます。コーヒー生産に限らず、農業では農地の開拓について問題視される事が度々あります。しかし、生産者と買い手の双方が環境の保護、持続性の重要さを認識する事で、農地に使用される分以上の取り組みが実施できる可能性は広がります。
ブエナビスタ農園

(左から、フアン・パブロさん、クレベルさん、パブロさん)
パレスチナ農園を訪問した翌日、更に車移動をしてブエナビスタ農園を訪問しました。このブエナビスタ農園のブルボンやゲイシャは、ONIBUS COFFEEでも最近まで取り扱っていたコーヒーです。
農園主のクレベルさんは3世代目のコーヒー生産者で、彼のお父さん、兄弟、親戚もいくつかの農園を保有しています。クレベルさんの兄弟で自身も生産者であるフアン・パブロさんは、一族の農園や知り合いの生産者のコーヒーを販売する為、イフアマカコーヒーという会社を立ち上げており、彼が経営しているカフェと海外マーケットへ販売を行っています。
以前にONIBUS COFFEEが取り扱っていた、ペルーのCOEロットである、ラパルマ農園は、このフアン・パブロさんのお父さんの農園です。スペシャルティコーヒーの生産は、2006年にお父さんであるパブロさんがスペシャルティコーヒーの生産を始めるため、土地を買ったところからスタートします。自分たちの土地の保全を行いつつ、コーヒー生産を可能にする為、スペシャルティコーヒーの生産に切り替えようと考えたことが一番の理由です。

彼らのコーヒーは、フアン・パブロさん自身が全てカッピングを行い、その品質がチェックされています。ブエナビスタ農園自体にはカッピングラボがない為、別会社のカッピングラボを借りて品質評価を行っています。品質向上の為の現在の課題は、生産時期により、収穫量に対してウェットミルやドライングベッドのキャパシティが不足することがあること。そのため今後は、ドライングベッドの増設を検討しているそうです。
生産地で私たちが見るもの

私たちは、生産者と顔を合わせて、「そのコーヒーが誰に、どのような環境で作られているのか、生産者や関わる人たちはどのような環境で働いているか」を直接見たいと思っています。それは、自分たちが提供するものを作ってくれている人の思いを受け取り、またその商品がどのようなものかを確実に確認した上で皆様に届けるためです。
カッピングでの品質確認はもちろんのこと、農園に訪れた時、私たちは以下のポイントを確認しています。
- 農園の状態(土壌、動植物の多様性など)
- 使用している肥料(コンポスト、有機肥料、化学肥料どの肥料を使用しているのか)
- 精製プロセス(欠点・不良豆の除去、パルピング・ドライングの方法など)
- ドライミルでの欠点豆選別プロセス
- 保管方法(保管場所の確認、またロットごとの管理方法など)
- 取引のある第三者機関(輸出業者などの確認)
など、、、これらのポイントは、これらをクリアしないと絶対に購入しないという基準ではありませんが新しい農園に訪れる際に、長期的な取引ができそうか判断する一つの指標になります。
ペルー訪問を通して感じた「第三者機関」の重要性

今回の訪問では、現地の事情を手探りで確認する必要があり、これまでの訪問先とは少し異なる状況でした。更に今回は、農園や生産者を取り巻く状態を理解する為に、私たちの積極性がより求められた訪問だったと思っています。その中で、今回のペルー訪問を通してより強く感じたことは、コーヒーの生産とそのサポート体制において、「生産者と共にクオリティ向上を目指す存在」の重要性です。この役割は、現地の輸出業者が担っていることが多いです。
私達は、トレーサビリティに重きを置き、実際に現地に足を運び、私たちが取り扱うものの透明性を高められるように力を入れています。しかし、コーヒーの生産において、より重要であると言えるものの一つが、コーヒーの品質の安定性です。そしてこれは、余程の頻度で産地に足を運ばない限り、私たちが直接的に関わるのは難しい部分です。
コーヒーが農作物である以上、予測できない自然条件の中で品質を保つのは並大抵の努力ではありません。それでも、彼らは日々忍耐強くコーヒーを作り続け、その努力と忍耐は賞賛に値します。しかし、特にスペシャルティコーヒーは、品質がものをいう世界。適切に品質を判断するスキルと、より良い品質を追求する為の試行錯誤が日々求められます。生産者の努力だけでは持続可能な生産やマーケティングを賄うのは難しいこともあり、現地でサポートしてくれるパートナーを持つことも重要になってきます。
このサポートが成果に直結していることを実感することは多いですが、実際にどのくらいのサポートを受けられるかは、団体や地域ごとの状況によって異なります。生産者がサポートを必要とし、それに対して有益な情報が共有されているのか、それとも生産者自身で全てを賄える環境にあるのか。前者の場合は特に、現地での輸出業者が果たす役割は大きく、生産者と市場を繋ぐ架け橋として、双方にとって必要な情報やサポートを提供し、持続可能な生産体制を築くための鍵となります。その為、私達は、農園のみではなく第三者機関も含めて、包括的に確認することが重要だと考えています。

今回のペルー訪問から、コーヒー生産における持続可能性は、生産者一人ひとりの努力だけでなく、強力なパートナーシップと支援体制によって支えられるものだと感じました。私たちはコーヒーを買う側として、その視点を忘れる事なく関係性の構築に尽力し、良いコーヒーを届けて行けたらと思います。
Text and photos by Chiaki Kuwahara




![エチオピア / グジ・シャキソ [ナチュラル]](http://onibuscoffee.com/cdn/shop/files/ethiopia_bcab6c39-5789-4482-84b1-2fe9af6cfe35.png?v=1725346118&width=533)



![コーヒーギフト[オニバスブレンド&シングルオリジンセット]](http://onibuscoffee.com/cdn/shop/files/DSCF6400.png?v=1764237384&width=533)
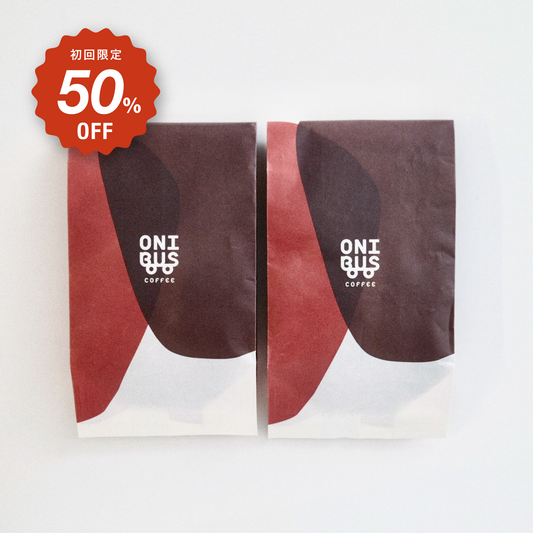
![コーヒーギフト [オニバスブレンド&カップ・ソーサーセット]](http://onibuscoffee.com/cdn/shop/files/DSCF6421-2.jpg?v=1764240210&width=533)