- スペシャルティコーヒー
ルワンダ訪問レポート2025~分かち合い、育むコーヒー

6月、ルワンダでは収穫期が落ち着いた乾季の始まりの時期。ONIBUSは、毎年この時期にルワンダを訪問するのが恒例になっています。
ONIBUS代表・坂尾が初めてルワンダを訪れたのは2014年で、今回は8度目の訪問です。一方で、私にとっては、今回が人生で初めてのルワンダ、アフリカ大陸、そしてコーヒー農園訪問もこれが初めてでした。
わずか5日間という滞在ながら、この訪問で得た学びと気づきは計り知れず、帰国後の今もなお、赤土の上で笑顔を見せてくれたルワンダの人々の姿が心に焼き付いています。
今回の旅の主な目的は、「Dukundekawa Cooperative」の再訪。本記事では、その体験を中心にご紹介します。
※ルワンダのコーヒーや国の特徴について、今までの経緯を詳しく知りたい方は、過去のブログをご覧ください!
https://onibuscoffee.com/blogs/news/146
https://onibuscoffee.com/blogs/news/147
Dukundekawa Cooperativeとは?

ルワンダ北部ガケンケ郡にあるONIBUSでもおなじみのンカラ(Nkara)、ルリ(Ruli)、ミビリマ(Mbilima)といったウォッシングステーション(CWS)を運営する農協です。2000年に約300人のメンバーでスタートし、現在は1,193世帯が所属しています。
コーヒーがやってくる道のりを辿って

気温19度の心地よい朝、Dukundekawa Cooperativeへと向かいます。
午前7時に中心地キガリのホテルを出発し、車でおよそ2時間半の移動。目的地は、標高2,000mを超えるルリ地区です。舗装路を抜けると赤土のデコボコ道に入り、丘を登り下りしながら奥地へと進んでいきます。ルワンダは「Land of One Thousand Hills(千の丘の国)」と呼ばれており、どこを見渡しても地平線はなく、丘が幾重にも連なっています。
午前9時過ぎに、ルリ地区にあるDukundekawa農協の本部に到着しました。出迎えてくれたのは、ここで働く女性たちによる舞と歌での歓迎。若い踊り手から、ご年配の農家の女性まで、オレンジ、緑、ピンクといった色とりどりの鮮やかな衣装。軽やかな手拍子と太鼓と鈴。心に響く歌声。これまでに受けたことのない暖かな歓迎に、一同大感動でした。
Dukundekawaに所属するメンバーのうち約80%が女性です。その背景には、1994年のルワンダ虐殺によって80万人以上が犠牲となり、未亡人や孤児があふれた社会状況があります。あれから30年が経った今、女性たちが笑顔で働き、コミュニティを再建している姿は、とても勇敢であり、偉大なものに映りました。
メンバーの生活を支えるDukundekawaの挑戦

マネージングディレクターのアーネストさんとキャッチアップ。今年の取り組みや進捗についてお話を伺いすると、この一年間だけでも新たな施策が進められていることがわかりました。
-
経済支援の拡大:以前からあるファンドの拡充。無利子で組合員が借り入れ可能(参考:銀行の金利は約18%)
-
ミルク工場のキャパシティ拡大:加工施設と最新鋭のミルクタンカーに投資し、衛生的な牛乳を地域に供給
-
ECD(幼児成長支援施設)の運営開始:従業員や地域住民の子どもたちのために開設。定員60名予定のところ、すでに50名超を受け入れており、早くも拡張を検討中
-
ミミズコンポスト導入:コーヒーパルプとミミズによる堆肥化で、農家への持続可能な資源循環を実現
得られた収入が、次なる設備投資や教育・福祉といった地域社会への再投資へとつながっている。そうした循環が地域の経済的自立を着実に後押しし、未来へ向けた力強い一歩になっていることに、深い感銘を受けました。
充実の設備
この農協の一番の特徴は、ウォッシングステーションだけでなく、ドライミルの設備もあることです。ドライミルとは、乾燥まで終えたコーヒー豆を出荷できる状態に仕上げていく、いわば最後の工程を行う場所。豆の脱殻から選別、袋詰めまでを自社のドライミルで一貫して行っています。
実際の流れはこんな感じです:
-
脱殻(ハルリング)
乾燥し終えた豆からパーチメント(殻)を取り除き、中のグリーンビーンを取り出します。 -
各種の機械選別
・比重選別機:重さで未熟豆などを取り除く
・サイズ選別機:豆の大きさを均一に揃える
・色彩選別機:発酵やカビ、虫害による色の異常を検知して除去 -
ハンドピック
最後は人の目と手による丁寧なチェック。欠点豆を1粒ずつ取り除いていきます。 -
袋詰めして保管・出荷へ
こうして選び抜かれた豆だけが袋詰めされ、ようやく出荷へと向かいます。
ルワンダの農協やウォッシングステーションは、チェリーをパーチメントにするまでを担うことがほとんどで、出荷前の最終加工を施すドライミルは別会社に委託するのが一般的です。ドライミルも運営し、収穫から出荷までの一連の工程を農協内で完結させるのはルワンダのコーヒー生産者グループの中でも稀なのです。
ドライミルを自社保有していることで
-
収穫から輸出まで一貫した品質管理が可能
-
コストの削減や利益率の向上につながる
-
トレーサビリティの信頼性が高まる
-
農協としての自立性・交渉力が高まる
という様々なメリットがあります。どこを見ても妥協がない徹底した品質管理。本当に頭が下がる思いです。
Dukundekawa 訪問の前日には、豆の輸出を行っているRWASHOSCCOのラボにて品質を確認済み。鮮やかな酸質とクリーンで華やかな質感、甘い余韻のあるDukundekawaのコーヒーの素晴らしさの理由がわかった気がします。
持続可能な生産を支えるフェアな支払い
コーヒー農家はDukundekawaのウォッシングステーションに新鮮なコーヒーチェリーを持ち込んだ時点で最初の支払いを受け取ります。チェリー1kgあたりの設定価格は、ルワンダ政府が収穫期の初めに国家農業輸出開発委員会(NAEB)を通じて設定する最低農場価格に連動しています。Dukundekawaの組合員には、この価格を上回る公正な価格が支払われます。
※NAEBは、2025年1月25日からコーヒーチェリー(完熟)の最低買付価格を 1kgあたりRWF 600(約US$ 0.42)に引き上げました。これは前年のRWF 480から、約25%の引き上げとなります。
そして重要なのは、農協が出荷したコーヒーの品質や市場競争によって得られたプレミアム(Organicや女性生産者等)に基づいて、2回目の支払いを受け取れるという点です。
プレミアがつくことによる主なメリット:
-
収入の増加:販売後に追加の支払いがあり、生活が安定しやすくなる
-
高品質や有機栽培へのやる気が生まれる:より良いコーヒーを作るインセンティブになる
-
女性や有機農家などへの公正な評価:働き手の多様性と公平性が守られる
-
地域や環境への再投資が可能に:教育・医療・インフラや環境保全に役立つ資金になる
収穫時に最低価格が保証されていて、さらに品質や取り組みに応じたプレミアが支払われる仕組みは、農家にとって安心感がありつつ、良いコーヒーづくりへのやる気にも繋がります。品質や取り組みに対する正当な評価がしっかりと反映されていて、そのプロセスの透明性とフェアさに強く信頼を感じました。コーヒーの売上が、誰にどう還元されるのかが明確で、そこに無理や矛盾がなく、地域の人たちが納得感を持って関わっている姿が印象的でした。
ソイルプロジェクトの視察
高い品質と、それを持続可能なものにする取り組みを行うDukundekawa。ONIBUSが彼らと一緒に取り組んでいるソイルプロジェクトは今年で3年目を迎えました。今回も先述の3つのウォッシングステーションとその地域でソイルプロジェクトに携わる農家を訪ねました。
ルリでは、バナナ畑のすぐ隣にあるコーヒー農園で仕込んでいるコンポストを確認。週1回の攪拌により順調に発酵が進んでいました。内部は温かく、菌糸も広がっていて良い状態。実際にコンポストを使用しているエリアでは、土の色が濃く柔らかく、コーヒーチェリーの収穫量が倍になったという農家さんの声も。
ミビリマでは、地域リーダーのボスコさんの農園(アグロフォレストリー実践中)を視察。ソイルプロジェクトのメンバーによるコンポスト作りのデモンストレーションも行われ、初年度には手探りだった作業も、今や迷いなく手際よく進行していて、スキルがしっかりと根づいていることが感じられました。
どのエリアでもコンポストを使った土づくりの成果が着実に現れてきていることを実感しました。
ンカラに移動し、ナチュラルとハニープロセスの乾燥工程を見学。乾季に入り、加工のメインはウォッシュトプロセスから、より天候に左右されるナチュラルやハニーへと切り替わったタイミングでした。ナチュラルは乾燥にかかる時間が14〜21日、ハニープロセスも手間がかかります。ハンドピックも丁寧なされ、手仕事の積み重ねが味に直結していることを目の当たりにしました。
こうして3地域を巡る中で、土壌づくり・栽培・加工のすべての工程において、コーヒーがいかに丁寧に扱われているかを実感しました。それぞれの工程に込められた想いと工夫の深さに、ただただ感銘を受けました。
ONIBUSでは自由が丘と那須でもコンポスト活動をしています。この取り組みが、ルワンダの地でどのように実践され、土や木々、そして人々の暮らしに影響を与えているのか――ソイルプロジェクトの本質と可能性を、自分の目と肌で体感することができたと思います。
初めての産地訪問を経て

この日だけでも、農協や農園で働く200人以上の方々と出会いました。言葉が通じない場面も多くありましたが、どこへ行っても皆さんが笑顔で迎えてくれました。手を振ると、満面の笑顔で手を振り返してくれる彼ら。
「どうしてそんなに笑っているの?」と尋ねると、
「あなたたちが来て、豆を買ってくれるから嬉しい」と、まっすぐに答えてくれたのがとても印象的でした。そのひと言に、すべてが詰まっているように感じました。
私たちの日常にある一杯のコーヒー。
その背景には、誰かの暮らしや努力、そして誇りがしっかりと存在している。それを実際に感じることができたのは、本当に大きな経験でした。
ルワンダという国は、1994年のジェノサイドという大きな悲劇を経験し、そこから30年かけて、少しずつ社会を立て直してきました。今もなお、その再生のプロセスは続いており、癒えない痛みや葛藤もきっとあるはずです。それでも前を向き、笑い合い、手を取り合いながら暮らす人々の姿に、私は大きな勇気と希望をもらいました。今回出会ったルワンダの人たちは、誰もが笑顔を絶やさず、生きる力に満ちていて、その強さと優しさに、深く心を動かされました。
私たちが日常で当たり前に感じている「便利さ」や「所有すること」とは異なる、 “分かち合いながら生きる”という姿勢がここには根づいていて、本当の意味での豊かさとは何かを、改めて考えさせられました。
ONIBUSが掲げる「コーヒーで、街と暮らしを豊かにする。」というビジョン。それは、誰かひとりが実現するものではなく、関わるすべての人の手で育てていくものだと思います。ルワンダの農園で働く人々のまっすぐな眼差し、彼らを支える現地のコミュニティ。そして、日本で豆を選び、焙煎し、バリスタが丁寧に一杯のコーヒーを淹れるまで――そのすべてのプロセスに関わる人たち、お客様、街や地域。そういったたくさんのつながりの中で、このビジョンは今、生きています。
一杯のコーヒーの向こう側に、遠く離れた誰かの暮らしや祈りがあるということ。それを感じながら、私自身がコミュニティに還元できること。これからも日々、そこに向き合っていきたい。そんな思いを新たにした、かけがえのない訪問となりました。
by Masashi Nakagome





![エチオピア / グジ・シャキソ [ナチュラル]](http://onibuscoffee.com/cdn/shop/files/ethiopia_bcab6c39-5789-4482-84b1-2fe9af6cfe35.png?v=1725346118&width=533)
![コーヒーギフト[オニバスブレンド&シングルオリジンセット]](http://onibuscoffee.com/cdn/shop/files/DSCF6400.png?v=1764237384&width=533)
![コーヒーギフト [オリジナルブレンド3種セット]](http://onibuscoffee.com/cdn/shop/files/DSCF63713-2.jpg?v=1764237315&width=533)

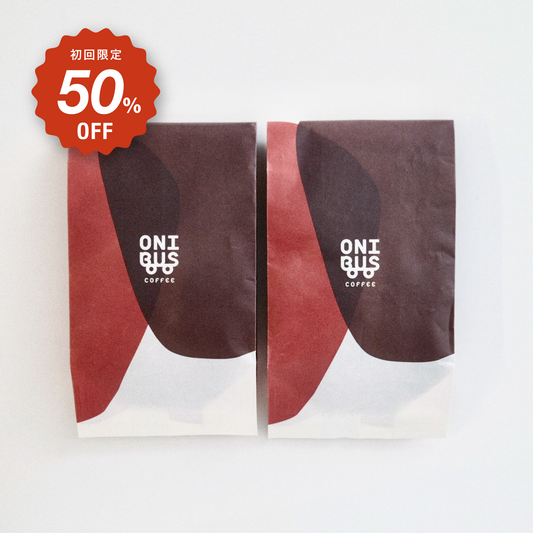
![コーヒーギフト [オニバスブレンド&カップ・ソーサーセット]](http://onibuscoffee.com/cdn/shop/files/DSCF6421-2.jpg?v=1764240210&width=533)
